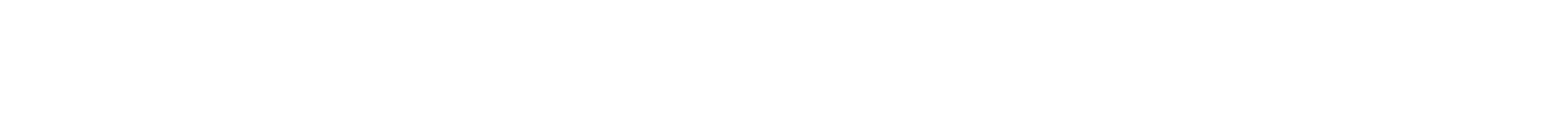vol.06
LUWEAVE-ISM
SPECIAL CROSS TALK
金融業界には高度な数理スキルを駆使して活躍するクオンツ(計量アナリスト)という職種があります。
今回は先端金融工学センターという、ITベンダーでは珍しい当社独自のクオンツ専門チームのメンバーに
クオンツを目指した背景や、仕事の面白さ、やりがいについて語ってもらいました。
メンバー
MEMBERS-

1994年入社
主席計量アナリスト/
先端金融工学センター長S.YAMAGUCHI
個性あふれるクオンツメンバーをまとめる先端金融工学センターのセンター長。チームマネジメントを行う傍ら、金融系イベントの講演、大学院授業での特別講師を務めるなど、幅広く活躍している。
-

2024年入社
計量アナリストR.KIDO
大学院で解析学を専攻。数字に触れることへの強い興味からクオンツを志し、ルウィーブに入社。現在はFX取引のアルゴリズム分析業務に携わり、着実にスキルアップを目指している。
-

2016年入社
計量アナリストT.TOUSE
大学院では純粋数学を専攻。新卒として入社し、クオンツとして大手金融機関常駐、当社製品KAI EMOTEを活用した会計CVA計算サービスなどに従事。現在は、株式取引をメインとした分析およびコンサルティング業務を行っている。

金融という枠を超えて、
幅広い分野での活躍が期待されるクオンツ
まず、クオンツについて教えてもらえますか?
R.Kクオンツとは、計量アナリストとも言い、さまざまなデータを高度な数理スキルや統計的知識を用いて分析し、課題解決へと導く専門職のことです。特に金融領域で強みを発揮しており、数理のスペシャリストとも言える存在だと思います。
S.YR.Kさんの言う通り、我々クオンツは金融の世界で、マーケットでの取引における公正価値の算出やリスク管理を行ってきました。最近では、電力自由化により、エネルギー業界でも金融と同様の取引が行われるようになりました。その結果、リスク管理の必要性が高まっており、この分野でもクオンツの活躍の場が広がってきています。
R.Kさん、T.Tさんは新卒でクオンツとして活躍されています。クオンツは高度な数理スキルが必要ということですが、2人はどのような学歴をお持ちですか?
R.K大学生の時は数学を専攻し、大学院に進んでからも解析学を研究していました。
T.T私も、大学院まで金融工学やプログラミングとはほとんど関係のない数学を専攻していました。
当社でクオンツになろうと思った理由はありますか?
R.K就職活動でも、数字を扱う仕事という考え方が前提にあり、クオンツか、アクチュアリー※1の2択で考えていましたが、いろいろな業種に関わってみたいという思いから、より自由度の高いクオンツを選びました。当社を選んだ理由も、その考えの延長線上にあって、クオンツとしてより多くの経験、学びを得て、視野を広げていけると思ったからです。
※1 保険や年金の分野で、保険商品の企画や保険料の算定などを行う数理スペシャリスト。
T.T私もR.Kさんと一緒で、アクチュアリーが選択肢にありましたが、幅広い分野で数学的素養を生かせるクオンツに魅力を感じました。当社を選んだのは、縁の要素が強いのですが(笑)。しかし、働いてみるとR.Kさんが言う通り、金融だけでなく、幅広い分野を経験できるというのが当社のクオンツの魅力かなと思いますね。
S.Y金融はもちろん、エネルギー分野などの業界にも関わっていけるのが、当社でクオンツになる魅力と言えます。また、金融機関ではフロント部門、ミドル部門それぞれにクオンツが在籍し、分業しているところもありますが、クオンツの役割の幅はさまざまで、すべての部門の業務に携わることができる金融機関があるのも、クオンツとして働く面白さかもしれませんね。


ITベンダーのクオンツ集団だからこそ、
多彩なスキルが身に付く
ITベンダーでクオンツの専門チームを持っている会社は少ないのですか?
S.Y以前は、当社の「先端金融工学センター」のように、クオンツ専門チームを持っている企業は少なかったのですが、最近はビジネスにおけるクオンツの重要性が認識されてきており、少しずつ増えてきている印象がありますね。AIも急激に発展していますので、予測モデルや取引戦略の最適化など、仕組みづくりの面で活躍の場が広がっており、ニーズの高まりに伴って、今後も増えていくかもしれません。
先端金融工学センターの役割とは?
S.Yもともと先端金融工学センターは、当社製品の1つである「Prélude Enterprise(以下Prélude )」という、銀行の金融市場取引業務を効率化するシステムの計算モデルをつくることを軸に据えつつ、他のクオンツ業務も手掛けていました。しかし、業務の幅が広がってくると、Préludeのクオンツはその開発業務だけに専念しようという話になり、Prélude以外のクオンツ業務を先端金融工学センターが受け持つようになりました。現在では、株やFXなどの金融市場取引におけるリスク管理、投資戦略サポートをはじめ、KAIEMOTEという地方銀行向けの会計CVA計算サービス※2、各種プロジェクトへのクオンツ派遣、当社内での新規事業への参画など、幅広い業務を手掛けています。
※2 融資先などが返済できなくなる可能性を数値化し、評価に反映させること


いろいろな業務を手掛けているんですね!では、2人はクオンツとして、どのような業務を担当しているのですか?
R.K私は、配属されてまだ間もないのですが、金融機関のお客様に対し、より高い収益を出すためのアルゴリズム開発を行うチームに配属されました。その中で、想定収益から乖離した日の分析調査などを担当しています。先輩方が残してくれた資料に目を通して、過去に同じように乖離した日がないか、その理由はどのようなものか、過去の履歴から見つけ出し、自分なりに理由を分析しています。中心的な業務をしているわけではありませんが、クオンツとしての経験を積んでいる段階です。
T.T私は2016年に入社して、2年目に大手金融機関に常駐し、金融機関のクオンツとして経験を積ませてもらいました。その後、社に戻ってからはKAIEMOTEの立ち上げ、また、別事業部が新規事業として検討していた気候変動に関するモデルづくりにも関わってきました。現在は、株式取引に関するデータの分析業務、その結果を元にしたコンサルティング業務を行っています。例えば、今まで手作業で行っていた業務を、モデルをつくってシステムに実装することで業務を効率化させる仕事があります。そこにはロジックとして数式が組み込まれますので、お客様に対してこのような分析結果が得られたという結果を示し、議論を繰り返しながら完成形に近づけていきます。数理のスペシャリストと聞くと、パソコンと向かい合ってコツコツしているイメージを持たれるかもしれませんが、おそらく皆さんが思うよりもコミュニケーションが必要とされる仕事だと思います。
S.YT.Tさんは、入社2年目に大手金融機関での常駐業務を経験したので、ITベンダーと金融機関のクオンツの違いを実感していると思いますが、どうですか?
T.Tそうですね、私たちITベンダーのクオンツは、正しくモデルを実装することを追求するするという仕事が中心になりますが、大手金融機関のクオンツは、そこに加えてそのモデルにどのような価値があるのかを経営層に伝え、意思決定をサポートするという役割も求められます。私たちも、分析結果やモデルなどをお客様にわかりやすく説明するコミュニケーション力が求められますので、大手金融機関のクオンツと業務をさせていただいた経験は非常に勉強になりました。
先端金融工学センターがあることによって、クオンツとしての視野が広がり、仕事の面白さややりがいにもつながっているのでは?
R.K仕事の面白さという面では、私にできることはまだ限られているのですが、その中でも自分なりに立てた仮説を裏付けるような証拠が発見できた時はすごくやりがいを感じます。先ほども日々の業務としてFXの想定収入から乖離があった日の分析調査をするとお伝えしましたが、乖離した理由を、根拠を示しながら矛盾なく構成していくのが面白いと思っています。
また、先端金融工学センターの魅力としては、先輩方の存在ですね(笑)。皆さんすごくいい人ですが、仕事に関してはとても厳しく、自分なりに自信を持って考えた仮説も、先輩から見たら“まだまだ”ということが多々あります。数理スキルはもちろんですが、論をどのようにわかりやすく説明できるかという説明力やコミュニケーション力も求められるので、クオンツとして鍛えられる環境だと思いますね。
T.T私自身も金融知識はほとんど皆無の状態でクオンツになり、最初は全然できなかったのを覚えています。そんな中で、常駐業務をやらせてもらったり、新規事業に携わらせてもらったり、幅広い経験を積めているのは先端金融工学センターがあったからこそだと思います。また、クオンツが活躍できる領域は、金融に限らず、エネルギー関連プロジェクトや、気候変動のプロジェクトのように、今後も新しい取り組みがどんどん増えてくると思います。そうした、さまざまなプロジェクトにクオンツとして関われるのも、先端金融工学センターならではのメリットだと思いますね。
S.Y手前味噌になってしまうのですが、先端金融工学センター内にクオンツ(計量アナリスト)は7名※3おり、全員が自分の仕事に誇りを持っています。携わっている仕事は異なりますが、プロフェッショナルとしての意識が高く、貪欲に新しいことを吸収しようとしています。勉強会や情報交換なども行うなど、一人ひとりの思いと行動が先端金融工学センターの存在意義を高めていると思います。
※3 2025年2月現在


若いうち貪欲にスキルアップを。
いずれは特定分野の第一人者と言われる
クオンツになってほしい。
少数精鋭の先端金融工学センターのクオンツチームですが、今後、どんな人に仲間になってもらいたいですか?
R.K自分にも言えることなのですが、学び続ける姿勢がとても大切だと感じています。数理知識だけでなく、その業界について深く知り、コミュニケーション力も磨いていかなければならないと思います。とにかく成長するんだ!というマインドを持っている人と、一緒に働けたら楽しいと思います。

T.Tクオンツが関わる仕事は、日々情報が更新されるため、お客様にサービスを提案できるようアップデートしていく必要があります。私自身も心掛けているのですが、自分から新しい情報をキャッチアップしていける人が望ましいのではないかと思います。また、自分の考えを持ち、積極的に行動できることも大切です。メンバーと議論し、考えを共有し合うことで、お互いに影響しあい、高め合えればとてもいいと思いますね。
S.Y若いうちは会社の売上等を考えずに、自分のスキルアップをメインで研鑽を積んでもらいたいと思います。T.Tさんが新規事業の立ち上げでクオンツとして参画したという話がありましたが、事業が成功すれば業界の第1人者になる可能性だってあります。そうなれば、自分がやりたいことも見つかるはず。落ち着かずに、興味関心のあることには、失敗を恐れずにどんどん前のめりで挑戦してほしいと思いますね。
※所属・役職、部署名は取材当時(2025年1月)のものです。
LUWEAVE-ISM 06

── 高い志を胸に抱き、チームワークを大切にしながら自分を磨き、成長していく。そして仕事を通じてお客様と社会に貢献する。対談を通して見えてきた社員達のそんな姿勢は、「ルウィーブ-イズム」と呼ぶにふさわしいもの。そして、社員一人ひとりのルウィーブ-イズムは当社の掲げる5つのクレド(信条)に深く根ざしています。
OUR CREDO
志を高くもち続けることは、簡単なことではありません。情熱的であった志も、本人が気付かないうちに、日々の仕事に忙殺され、少しずつ失われることも少なくありません。何かを達成したら、そこに満足し安住したい気持ちもあるでしょう。しかし、何かを成し遂げたら、本当は次の目的が見えてくるはずです。
「aim」という単語には「照準をあてる」という意味があります。何かを達成したら、次の目標に照準をあてる。「Aiming high」とは、その繰り返しです。
私たちは、つねに高い目標を自ら掲げ、ICT業界の枠を超える独自の価値を創造し、お客さまや社会に貢献します。
「truth」という単語は「真実」を意味します。ビジネスの場面では、競争のステージが変化し、真実の定義が変わる場合もあります。本質を追求し続けることが、ビジネスにおける「真実」です。
本質を追求することは、簡単なことではありません。過去の習慣、上下関係、技術常識などさまざまな慣習の壁に阻まれ、本質が見えなくなる場合がしばしばあります。また、本質を共有するためには、慣習の壁を打ち破る論理や、伝える勇気も必要です。腹を割った議論が必要な場合もあります。
私たちは、慣習の壁にとらわれず、何が大切なのかを感じ、考え抜き、共有することで、つねに本質を追求します。
私たちは、これまでの歴史の中で、社会のニーズを感じ取り、新しい価値を創造し続けてきました。他社が目を付けていなかった事業領域で成功を収め、新しい価値を社会に提供してきました。自由闊達な風土と、リスクを共有する勇気が、それを支えてきました。
「first」という単語は「最初に」を意味します。最初に何かを行うことは、それ自体に意味があります。誰よりも先に考え行動し、最初に何かを成し遂げた者にしか得ることのできない、貴重な価値があります。
私たちは、ニーズを感じ取り、つねに他社に先駆ける価値を創造することで、ICT業界の先駆者として時代を牽引します。
あきらめることは、いつも簡単なことです。あきらめた瞬間に、さまざまな言い訳や慰めの言葉が、自らの「あきらめ」を正当化してくれます。あきらめないことは、困難と勇気を伴います。あきらめないことで、揶揄されることがあるかもしれません。
しかし、なすべきことにこだわり、あきらめないことで、私たちは成長することができます。あきらめないことで、独創的な価値を創造したり、お客さまの期待に応え、さらに期待を超える品質を提供することができます。
私たちは、お客さまをはじめ、相手に与えた期待値を超えるまで、あるいは自らの考えやアイディアが相手に伝わるまでは、決してあきらめず、こだわり抜きます。
「One family」は、私たちが、日本オリベッティとして事業活動を行っていた時代から、私たちの中に永く培われてきた大切な精神の一つです。私たちの先人は、「One family」の精神をもって、あらゆる困難に立ち向かい、新しい価値を創造してきました。その精神はいまでも、私たちの誇りです。
「family」という単語は「家族」を意味します。一つの家族のような強い絆や団結力は、組織としての強い力であり、企業が成長していく糧となり得ます。
私たちは、これからも「One family」の精神を大切に継承し、目的を共有し、助けあい、成長していきます。